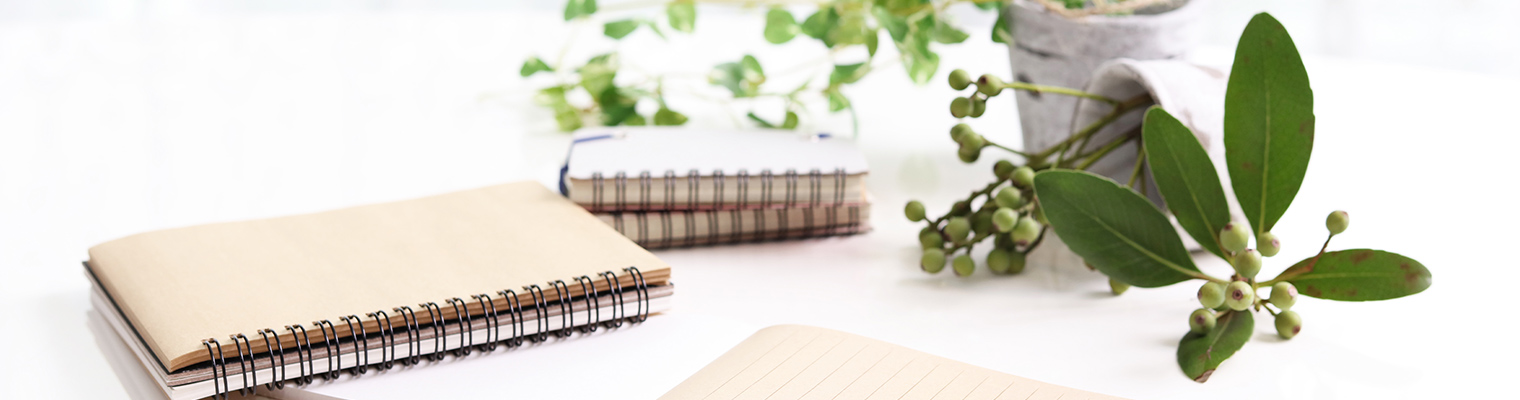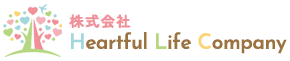リハビリとは?リハビリの役割と行う意味

「自分らしく生きること」を軸に、リハビリとはなんなのか、そして実際にどのような流れで行われるのかを解説していきます。
目次
- ○ リハビリテーションとは
- ○ 病院・治療院のチェックポイント
- ○ リハビリの流れ
- ・急性期のリハビリ
- ・回復期のリハビリ
- ・維持期のリハビリ
- ○ 特に大事なのは回復期のリハビリ
- ○ リハビリの継続をサポートしてくれる治療院
リハビリテーションとは

「リハビリテーション」が機能回復訓練を指すだけではないことは前述のとおりですが、では具体的にどういったことを指すかというと、病気や怪我などによってそれまでのような生活を送れなくなってしまった方を対象に、できる限りその日々を取り戻せるようにし、あるいは「こういうことをしてみたい」という望みを叶えられるようにすることがリハビリテーションの真の意味するところです。
リハビリには主に下記の6種類が存在します。ここからも、機能回復訓練のみを指す言葉ではないとわかるのではないでしょうか。
医学的リハビリテーション病院など医療機関で行われるリハビリテーション。心身の機能、能力回復を目的としています。
職業的リハビリテーション職業訓練校や地域障がい者職業センターなどにおける、就労を目的としたリハビリテーション。
教育的リハビリテーション養護学校や特別支援学級、肢体不自由施設などで行われる発達分野におけるリハビリテーション。
社会的リハビリテーション社会参加、復帰を目的に、本人の身体的状況や生活を営む上で妨げとなるバリアを解消するリハビリテーション。上の3つのリハビリテーションの土台になることもあります。
介護リハビリテーション介護認定を受けている方を対象とした、日常生活全般をリハビリと捉え、機能維持を目的としたリハビリテーション。できる限り自身で行うことで自立を促します。そのため、当人の能力や練習している内容などを医療スタッフだけでなく家族も把握し、情報を共有しながら連携していくことが大事になります。
後述する理学療法士(PT)や作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)などリハビリ専門職の従事者が要介護者のご自宅に伺ってサポートする訪問リハビリテーションが行われることもあります。訪問リハビリのメリットは、リラックスできる環境で取り組めること、家族と同居している場合は情報共有がスムーズに済むこと、個別でリハビリを受けられるため配慮の行き届いた細やかな対応がなされることなどが挙げられるでしょう。
リハビリテーション工学(参加支援工学)義肢装具や住宅や施設、交通機関のバリアフリーなど、リハビリテーションにおける工学的アプローチ全般を指します。
今回はこの中でも医学的リハビリテーションについて解説しますが、リハビリを行うのは、国家資格を取得していないと担うことができない、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)など。
PTは体操や運動、マッサージなどによって、日常生活に必要な基本動作を行う機能の維持・回復を、OTは家事など日常生活における作業動作、そして手芸、工作など生活の中で行われる趣味、娯楽を通じて、心身の機能や社会適応力の維持・回復を図り、STは主に発声、発語など言葉を使ったコミュニケーション訓練、嚥下の機能訓練を行うことで社会生活へのサポートを行います。
患者ひとりひとり、症状も気力も環境も異なるため、リハビリスタッフだけでなく、医師や看護師などすべての医療スタッフ、医療相談員がチーム一丸となって取り組むことが必要です。
また、患者にも自ら積極的にリハビリと向き合うことが求められますが、それには息の合ったチームが要されるため、病院や治療院の選び方も重要となります。
病院・治療院のチェックポイント

・院内の雰囲気、スタッフの対応が合うかどうか、人数が十分かどうか
・頻繁に(できれば通年毎日)リハビリを実施しているかどうか
・相談できる担当スタッフがいるかどうか
主にはこれらが病院・治療院選びの際のポイントとして挙げられます。退院後も通う可能性があることなどを踏まえると、家や駅から近いことも加えたいところですが、その点を優先させるとどうしても上記の点で多少の不満があっても我慢してしまうこともあるかもしれないので、また、訪問リハビリを受けるという手もあるので、あくまで上の3つに注目しましょう。
リハビリの流れ

一般的にリハビリ治療は急性期・回復期・維持期の3段階、もしくはその前後に予防期と終末期を加えて5段階に分けて考えられることが多いです。その時期の区分について科学的な根拠はないともいわれていますが、それぞれの状況に合った治療法を行うべきだとされています。
急性期のリハビリ
急性期は症状が現れ始めた時期なので、患者の負担は身体的にも精神的にもとても大きいです。容体が急変することも多いため、常に迅速かつ的確な判断が必要となります。
そのため、もちろん安静も必要ですが、無理のない範囲で体を動かさないと廃用症候群を招き、体を動かしにくくなるため、少しずつリハビリを始めていきます。症状にもよるため、具体的な訓練方法は明らかにしにくいですが、たとえば長時間体を横たえる必要がある場合には、寝たきりになってしまわないよう関節可動域訓練、筋力増強訓練、日常生活動作訓練(「Activities of Daily Living」を略して「ADL訓練」とも呼ばれます)などが行われます。
通常はこの後、回復期に移行しますが、軽症例などは回復期を経由せず、あるいは非常に短期間の内に経由し、治療を終えるケースもあるため、急性期でのリハビリも重要視されています。
回復期のリハビリ
症状が急変する可能性、そしてそれに迅速に対応する必要がある急性期を経て、回復期はリハビリに集中する時期といえます。「病気や怪我を負う前の生活により早く戻ること」、具体的にいうと、たとえば入院している場合は、「在宅復帰を目指す」ことを目的としてリハビリが行われる期間です。
急性期と比べると容体が急変する可能性は低くなりますが、それでも完全にないとはいいきれず、また、合併症のリスクも残っているため、ケアできる万全の状態を維持したまま体の機能の回復を図っていきます。
退院後の生活に不安を感じることなく社会復帰できるよう、機能回復訓練や治療のサポートだけでなく必要な情報の提供、社会生活に及ぶあらゆる関連機関との調整がなされます。
維持期のリハビリ
回復期の後に行われるリハビリは、急性期、回復期に回復された機能を維持することを目的に行われます。通院の可能性はありますが、基本的には医療機関によるリハビリというよりも自宅でのリハビリが主になります。著しい機能改善を見込むのは難しいですが、時間をかけて反復動作訓練などを行うことでじっくりと向上させていきます。
また、廃用症候群予防の面でも、積極的に活動していくことが重要となる時期です。寝たきり、引きこもり、そして再発を避け、体力を維持するために、社会活動に参加できる環境を調整していくことが必要となります。
場合によっては生活習慣病などにかかり、入退院を繰り返してしまうケースもあるため、精神面でもサポートしてくれる病院・治療院選びが必須でしょう。経過がゆっくりで、医師や医療スタッフと向き合う時間も長くなるので、なおさら信頼できるかどうか、相性がいいかどうかは重要です。
特に大事なのは回復期のリハビリ

回復期はリハビリに集中する時期だと先述しましたが、入院している場合はその入院生活すべてがリハビリと捉えられるため、動作ひとつひとつが目的をもち、自身の力で行えるようサポートされます。特に食事やトイレなど、日常生活において必要不可欠であり、また、尊厳にもかかわる部分は手厚く自立に向けて支援されます。
ただし、回復期リハビリテーション病棟を利用する場合、発症から入院までの期間、また、入院できる期間に制限があることはあまり知られていないかもしれません。病気によってその期間は異なりますが、どの場合においても、より早くその密度の濃いリハビリを受けられるかどうかが回復までにかかる時間と回復度合いに影響を与えます。
つまり、その期間にしっかりと自身がリハビリに臨める環境にあるのかどうかが一番大事になるので、病院・治療院の雰囲気、環境、そしてサポート体制をきちんと見極めて選ぶようにしましょう。事前に見学できる場合は、できる限り自分や家族の目で確かめた方がいいです。
リハビリの継続をサポートしてくれる治療院

期限が過ぎた後にリハビリを受けたいという場合は、鍼灸、マッサージ、整骨・整体などの治療院でしっかりとした施術が可能なので、ご自身の精神・身体に合った方法を選びましょう。たとえ、通っていた病院の医師が「もう機能回復は見込めない」と判断しても、その後の訓練次第で改善、回復するケースは多々あります。諦めないで今後の生活に向けて行動を起こし続けることこそが一番のリハビリといえるかもしれません。
もし自身や家族、周りの方がなんらかの疾患を発症し、リハビリが必要になった場合には、病気や怪我の治療だけ、もしくは機能回復だけを目的とするのではなく、その先にある日々の生活を見据えて、あらゆる選択、行動を起こすことが大事です。
疾患を抱えた当人が変化を恐れずに積極的にリハビリに臨むこと、そしてそういった方が安心して生活でき、もし機能障害が残ってしまっても適切に受け入れられる社会環境が必要なのです。そのためにはリハビリ対象となる本人だけでなく、周りの方々、ひいてはすべての方々がそういった社会を求め、築いていかなくてはいけません。